<12月のカレンダー
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
最近のコメント
各月の日記
- 2017年10月の一覧
- 2017年9月の一覧
- 2017年8月の一覧
- 2017年7月の一覧
- 2017年6月の一覧
- 2017年5月の一覧
- 2017年4月の一覧
- 2017年3月の一覧
- 2017年2月の一覧
- 2017年1月の一覧
- 2016年12月の一覧
- 2016年11月の一覧
- 2016年10月の一覧
- 2016年9月の一覧
- 2016年8月の一覧
- 2016年7月の一覧
- 2016年6月の一覧
- 2016年5月の一覧
- 2016年4月の一覧
- 2016年3月の一覧
- 2016年2月の一覧
- 2016年1月の一覧
- 2015年12月の一覧
- 2015年11月の一覧
- 2015年10月の一覧
- 2015年9月の一覧
- 2015年8月の一覧
- 2015年7月の一覧
- 2015年6月の一覧
- 2015年5月の一覧
- 2015年4月の一覧
- 2015年3月の一覧
- 2015年2月の一覧
- 2015年1月の一覧
- 2014年12月の一覧
- 2014年11月の一覧
- 2014年10月の一覧
- 2014年9月の一覧
- 2014年8月の一覧
- 2014年7月の一覧
- 2014年6月の一覧
- 2014年5月の一覧
- 2014年4月の一覧
- 2014年3月の一覧
- 2014年2月の一覧
- 2014年1月の一覧
- 2013年12月の一覧
- 2013年11月の一覧
- 2013年10月の一覧
- 2013年9月の一覧
- 2013年8月の一覧
- 2013年7月の一覧
- 2013年6月の一覧
- 2013年5月の一覧
- 2013年4月の一覧
- 2013年3月の一覧
- 2013年2月の一覧
- 2013年1月の一覧
- 2012年12月の一覧
- 2012年11月の一覧
- 2012年10月の一覧
- 2012年9月の一覧
- 2012年8月の一覧
- 2012年7月の一覧
- 2012年6月の一覧
- 2012年5月の一覧
- 2012年4月の一覧
- 2012年3月の一覧
- 2012年2月の一覧
- 2012年1月の一覧
- 2011年12月の一覧
- 2011年11月の一覧
- 2011年10月の一覧
- 2011年9月の一覧
- 2011年8月の一覧
- 2011年7月の一覧
- 2011年6月の一覧
- 2011年5月の一覧
- 2011年4月の一覧
- 2011年3月の一覧
- 2011年2月の一覧
- 2011年1月の一覧
- 2010年12月の一覧
YUNIKOさんの日記
(全員に公開)
- 2012年
01月30日
22:04 続・続・親愛なる絵テロリストさんに捧ぐ。
本家の方が完結しましたので、こっちも完結でっ!
ちょっと長くなっちゃいますので、2話連続アップで~
-------本 文------
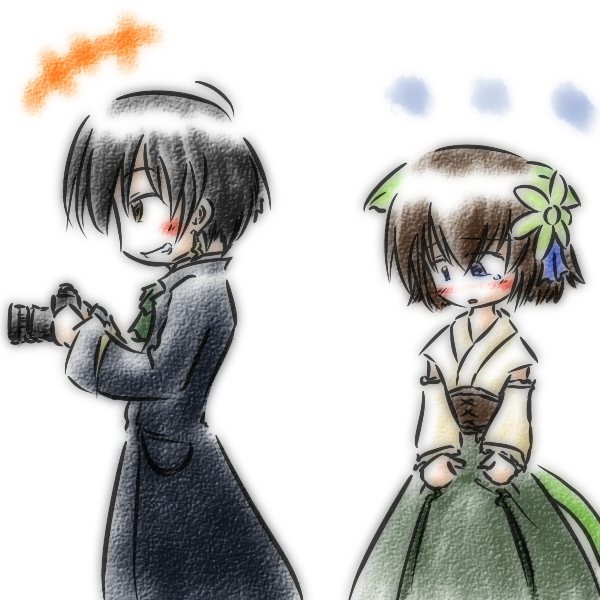
「にゃうにゃぅ・・・。また増えたのですぅ。みどりとご主人さまはどうなっちゃうのですにゃぁ・・・っく・・・えくっ・・・」
大粒の涙が鈴緑の眠たげな瞳に浮かび始めたのだった。それを見たミルキーは小さく舌なめずりをすると鈴緑の頬をそっとなぞり、
「そうですわ、私イイ事思いついたかもしれませんわ。」
ニャッコとアイに視線を送る。
「ミルル、なになに?」
ニャッコが私の胸元から顔を上げる。アイも構えたカメラを下ろしてミルキーの方を見る。
「この子、エメルの使い魔の鈴緑ちゃんでしょう?この子はエメルにべったりだから、私が急いで食べちゃわなくても後でゆっくり食べちゃえると思いますの。」
「え?そーなの?この子、緑ちゃんなの?」
ニャッコは驚いた表情で鈴緑を見る。ミルキーは涼しげな表情のまま
「だーかーらー・・・今日はアイもいることですし、まずはエメルを3人で美味しくいただいちゃって、その後この子もご主人様と一緒に・・・っていうのはどうかしらーと思ってぇ。」
胸元から、扇子を取り出し口元を隠す。
「ボ、ボクも?!ボクはこのカメラに収めるだけで満足なんだけど。そ、そりゃエメルは可愛いから一度はお手合わせしたいとは思ってたけどさ。」
アイは少し照れながら下を向き呟く。当然そのしぐさをミルキーが見逃すわけもなく、
「あらぁ?こんな機会なんてめったにないのですよ?アイもたまには自分に正直になりなさいな♪きっとステキな時間が過ごせると思いますけど?」
その扇子の裏側でミルキーにはどんな光景が浮かんでいるのか。アイの背中に電気が走る。アイの抑えていた衝動を引き出すかのように、
「そ、そうだね・・・。ボクも一度そっち側に立ってみたかったんだ・・・。」
スイッチが入ってしまった。アイの瞳は、いつものカメラマンとしての鋭さではなく獲物を前にした猛禽類のソレだった。私の顔から生気が抜ける瞬間だった。ニャッコも私から体を離すと、スッと立ち上がり私を見下ろす。その隙にと思うのだが、3人の異様なオーラに私の体は言う事がきかない。ニャッコが放れて軽くなった体に襲ってきたのは震えだった。
「な、ね?ちょっと・・・みんな?ニャッコ?ミルキー?アイ?なに?なに考えてるの?やめよ?だ、だ、だめだって・・・。」
私は必死に諭そうとするが、声が震えて・・・いや体が震えすぎてちゃんと言葉にならない。そんな私の姿にミルキーは少し扇子を下げると、三度紅い舌を艶やかな唇に這わせる。
「それでね、今日がステキな記念日になるように。そして全てが忘れられなくなるようにカタチとして残したいなぁって思いますの。」
その言葉を待っていたかのように部屋の扉が静かに開く。そこに現れたのは一人の剣士だった。しかし、その手に握られているのは剣ではなく一台の機材。どう見てもそれはビデオカメラだった。
「ごめんごめん、遅れちゃったかと思ったけど・・・。いいタイミングだったみたいだね♪」
その剣士は、ピンクの長い髪を軽くかき上げると手に下げていたカメラを肩に担ぐ。
「いいでしょう?今日はユニコに撮影お願いしましたの。これでステキな時間が全て記録されますわ。」
その一言がきっかけになったのか、その一言でこれから起こることが頭に浮かんでしまったのか、鈴緑の瞳から大粒の涙が一筋、二筋、それは止まることなく次々と流れ出した。
「だめ・・・だめ・・・だめです・・・っく、えっく・・・ご主人さまを守らないと・・・み、み、みどりがご主人さまを・・・守らない・・・と。」

鈴緑の小さな小さな手がキュっと握られる。涙が流れるその瞳は、怯える小動物のソレそのものであったが、その奥に小さく輝くものがあった。ユニコがカメラを構えたときだった。
「ふー、間に合ったっぽい?ぽい?もう、ユニコ置いてかないでよぅ。マイクって地味に重いんだからぁ。」
そう言ってまた一人、狐耳の少女が長いロケ用マイクを持って入ってきた。
「だって、メイさんが遅いんじゃんかー。でもこれからだからダイジョウブ♪」

「それじゃ、全員揃ったところで始めましょう・・・。これが本当の・・・」
「「「めくるめくカンノウの世界よっ!」」」
その時だった
「だっ・・・だめですーーーーーーーっ!ご主人さまにぃ、さーーーわーーーるーーーにゃーーーーー!」
部屋の壁が震えるくらいの鋭い声が響き渡る。しかし、
「ハイハイ、そこまで~」
「んにゃ?!にゃにゃにゃにゃにゃ!!」
今にも3人に飛び掛ろうとしたその体が宙に浮く。
「ホラホラ、あ・ば・れ・る・・・なっ!緑っ♪」
鈴緑の襟を掴んでいたのは、白い軍服を着た気持ち鼻眼鏡の少女。しかしその風貌は他と少し違っていた。頭には赤いヘルメット、右手にはプラカード大の看板を担いで。
「もーーーーー、ったくぅ、緑こんなに泣かせちゃってぇ。可哀想にぃ、キミらやり過ぎだってーの。ほら、緑これ見てごらん?」
ボロボロ流れる涙を、小さな手でキュキュッと拭うと、そこにあったのはいつも遊んでくれる見慣れたご主人さまのお友達の顔。
「ユ・・・ユウしゃみゃ・・・。ぐしゅ・・・にゃに・・・これ・・・」
眼鏡の少女が持っていた看板には
『ドッキリ 大成功☆』
の文字が・・・。

- ECOの創作